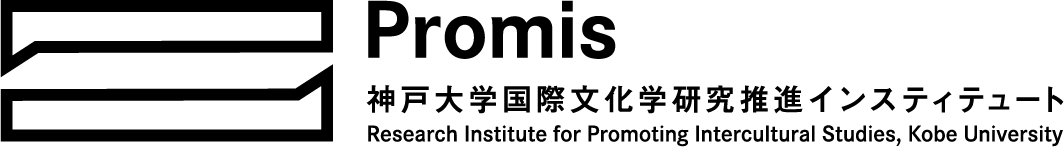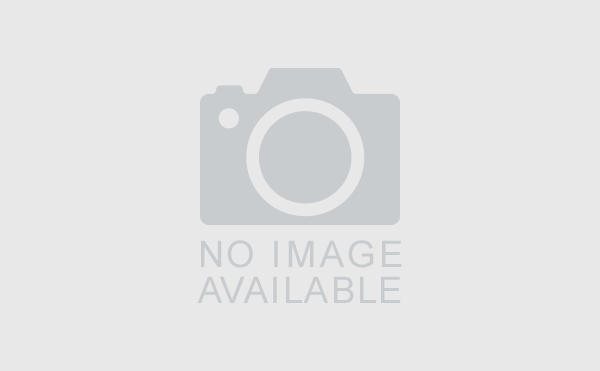Annual Research Report of Promis Vol.3(2024)
(Online)ISSN 2758-6634
(Print)ISSN 2758-6626

編集・制作/Editors:
ZHANG Jiahui, SUKIKARA Fumiko, UE Akiko, OTANI Shimpei, RAZGUI Yosri, YU Wen-hsin, TAN JOY Ann Faith, MATSUMOTO Atsuya
発刊日/Date of Publication:
31 March 2025
発行者/Publisher:
Research Institute for Promoting Intercultural Studies, Kobe University(Promis)
Annual Research Report of Promis Vol.3(2024)No.1: Contents
Annual Research Report of Promis Vol.2(2023)
(Online)ISSN 2758-6634
(Print)ISSN 2758-6626
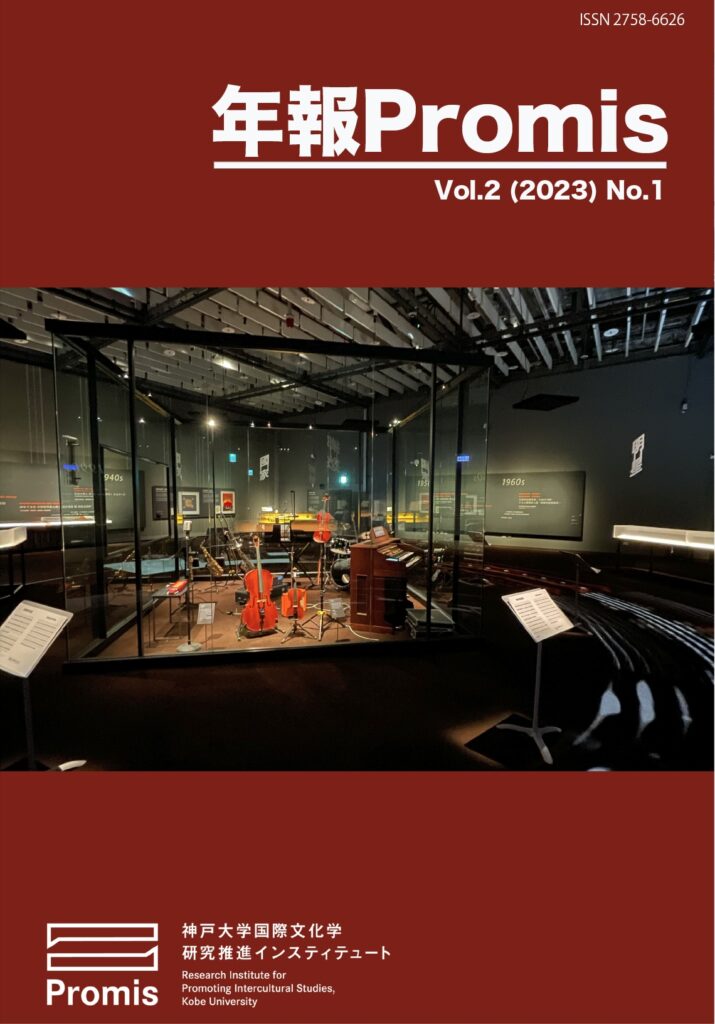
編集・制作/Editors:
YU Wen-hsin, UE Akiko, OTANI Shimpei, HUANG Po-Lung, SATO Ryosuke, HARADA Suguru, MATSUMOTO Yumiko
発刊日/Date of Publication:
31 March 2024
発行者/Publisher:
Research Institute for Promoting Intercultural Studies, Kobe University
Annual Research Report of Promis Vol.2(2023)No.1: Contents
Annual Research Report of Promis Vol.2(2023)No.2: Contents
シンポジウム「日本を選ぶ(残る)理由、日本を選ばない(去る)理由」報告書
Edited by KAMIZURU Hisahiko (Professor of Prefectural University of Hiroshima)
Annual Research Report of Promis Vol.1(2022)
(Online)ISSN 2758-6634
(Print)ISSN 2758-6626
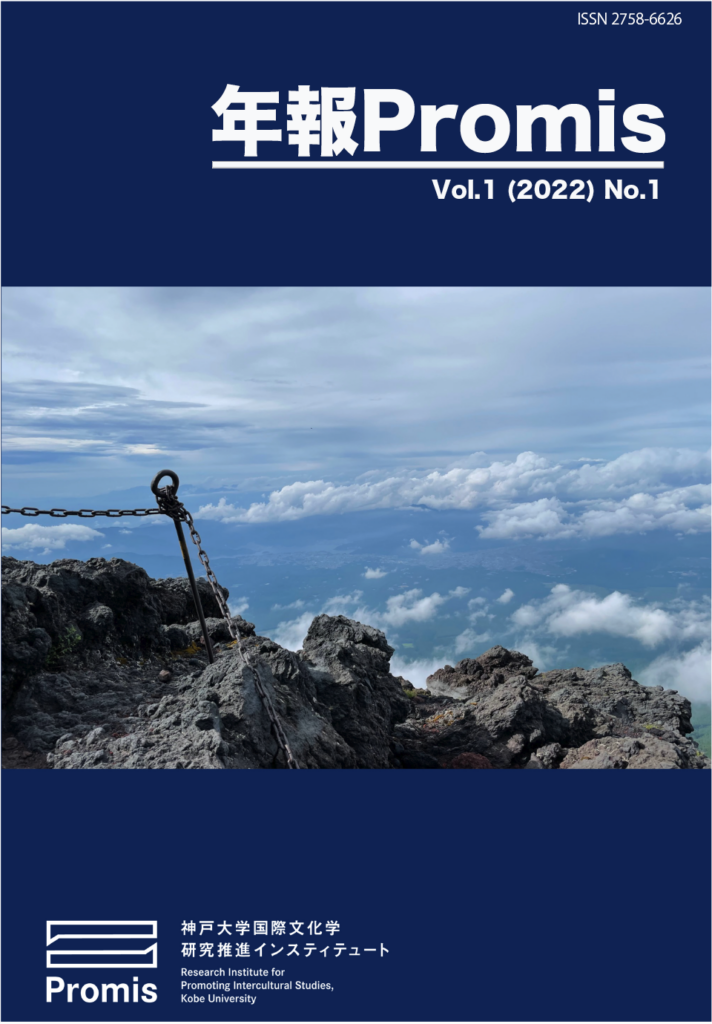
編集・制作/Editors:
YU Wen-hsin, OTANI Shimpei, HUANG Po-Lung, SATO Ryosuke, HARADA Suguru, MATSUMOTO Yumiko
発刊日/Date of Publication:
31 March 2023
発行者/Publisher:
Research Institute for Promoting Intercultural Studies, Kobe University
Annual Research Report of Promis Vol.1(2022)No.1: Contents
| Ⅰ論文・研究ノート | |
| 【論文】 2000年代以降の日本社会における新しいコミュニケーションスキル ―1974年~2019年の会話ハウトゥ本における「話力」をめぐる助言の変容から考察する― 桶川 泰(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 3-13 |
| 【論文】 ファン翻訳に関する研究の方向性の検討 —中国におけるロックファンによる翻訳の調査に基づいて— 朱 藹琳(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 14-24 |
| 【論文】 文化大革命期の内モンゴルにおける被害状況に関する考察 アルチャ(阿日査)(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 25-41 |
| 【論文】 蒙古軍政府成立前後における関東軍と徳王による募兵工作 白 那日蘇(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 42-61 |
| 【論文】 前衛書家上田桑鳩による周縁での試み ―作品の所在と「彩書」― 向井 晃子(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 62-78 |
| 【論文】 ユーモアスタイルに関する日中比較の予備的検討 林 萍萍(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 79-94 |
| 【論文】 EUにおける制度作用の考察 —After Hegemonyからの理論的示唆を基にして— 原田 豪(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 学術研究員) 宇野原 将貴(神戸大学国際文化研究科 博士後期課程) 宮本 聖斗(神戸大学国際文化研究科 博士後期課程) | 95-122 |
| 【研究ノート】 日本文化を背景とする「芸術」への岐路 ―合気道家多田宏インタヴュー― 向井 晃子(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 123-139 |
| 【研究ノート】 スタインバーガー ―1870年代におけるアメリカの太平洋進出を視座に― 矢野 涼子(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 140-150 |
| Ⅱ書評 | |
| The History of Computing, Doron Swade, Oxford University Press, 2022 野村 恒彦(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 153-154 |
| Ⅲ著書紹介 | |
| 単著『戦後前衛書に見る書のモダニズム—「日本近代美術」を周縁から問い直す』2022年、三元社 向井 晃子(神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進インスティテュート 協力研究員) | 157-158 |
| Ⅳ神戸大学創立120周年記念事業:国際文化学研究推進インスティテュート開設記念行事 | 159 |
| Ⅴ2022年度セミナー報告 | 163 |
| Ⅵ2022年度プロジェクト概要 | 197 |
| Ⅶ移住・移民研究センター活動概要 | 207 |
| Ⅷ地域連携センター活動概要 | 215 |
Annual Research Report of Promis Vol.1(2022)No.2: Contents
ドゥルーズとクロソウスキー、革命の思想と体験の模倣―『ドゥルーズと革命の思想』(以文社)をめぐって―開催記録![]()
鹿野 祐嗣(神戸大学国際文化学研究科助教) 編著
2021 Annual Research Report
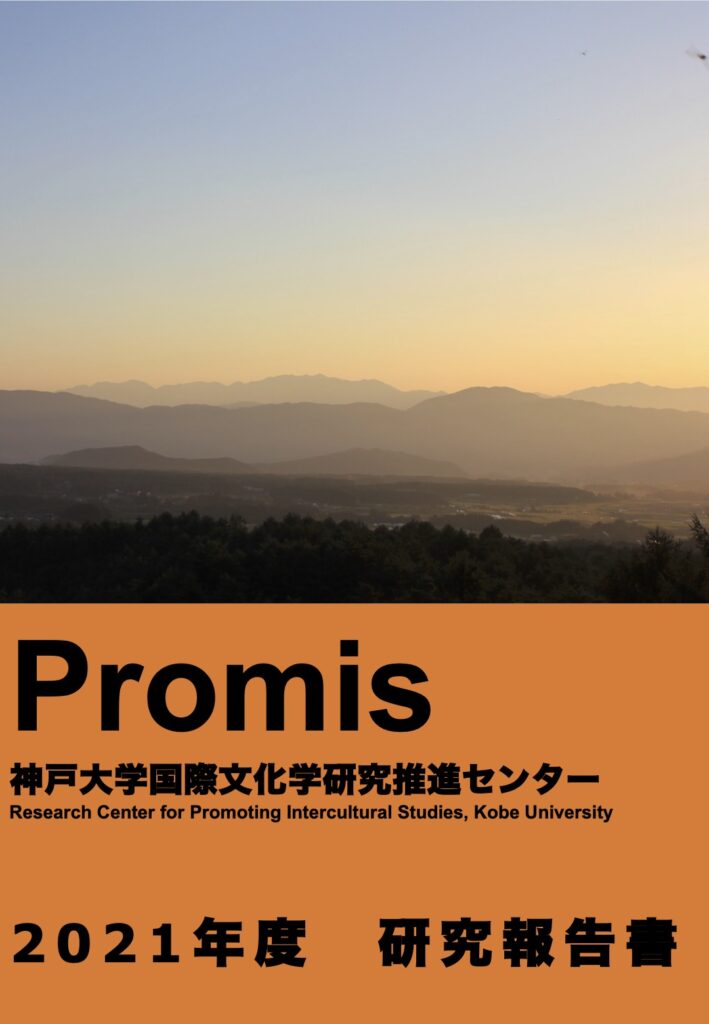
編集・制作/Editors:
OTANI Shimpei, KOBAYASHI Rune, SATO Ryosuke, HARADA Suguru, MATSUMOTO Yumiko
発刊日/Date of Publication:
31 March 2022
発行者/Publisher:
Research Center for Promoting Intercultural Studies, Kobe University
2021 Annual Research Report: Contents 
| Ⅰ.論文・研究ノート | |
| 【論文】 社会システム理論における〈中間〉概念の動態化 畠中 茉莉子(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 7-21 |
| 【論文】 Mittellage-Discourse in Twentieth Century Germany: Ernst Jünger’s Case Toshihiko Nogami (Promis Collaborative Researcer) | 22-51 |
| 【論文】 信頼の意味に関する日中比較―自由記述の分析を基に― 林 萍萍(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 52-71 |
| 【論文】 残酷な「異形化」―『ジョジョの奇妙な冒険』虹村兄弟と『鬼滅の刃』不死川兄弟の葛藤ー 植 朗子(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 72-87 |
| 【研究ノート】 コミュニケーション能力をめぐる社会科学研究とその課題 桶川 泰(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 87-94 |
| 【研究ノート】 欧州統合理論の再検討―新機能主義とリベラル政府間主義の比較からー 原田 豪(国際文化学研究推進センター 学術研究員) | 95-117 |
| Ⅱ.書評 | |
| 『なっとくする数学記号 𝜋、e、𝑖から偏微分まで』, 黒木哲徳、講談社ブルーバックス 野村 恒彦(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 121-122 |
| Ⅲ.2021年度セミナー一覧 | |
| Ⅳ.2021年度プロジェクト概要 | |
| 新しい「神話的物語」の創生と日本ポップカルチャー | 158 |
| 多文化共生における信頼感に関する国際比較研究ーー日中比較研究を中心に | 159 |
| 近現代ドイツにおける地理的「中間Mitte」の思想史:「中間民族Mittelvolk」自己像の生成と類型 | 160 |
| 日本人学習者の中国第三声習得に関する研究 | 161 |
| 「モノ」のエスノグラフィー:アート、伝承文学、エコロジーにおけるポスト・ポストヒューマニズムの研究 | 162 |
2020 Annual Research Report
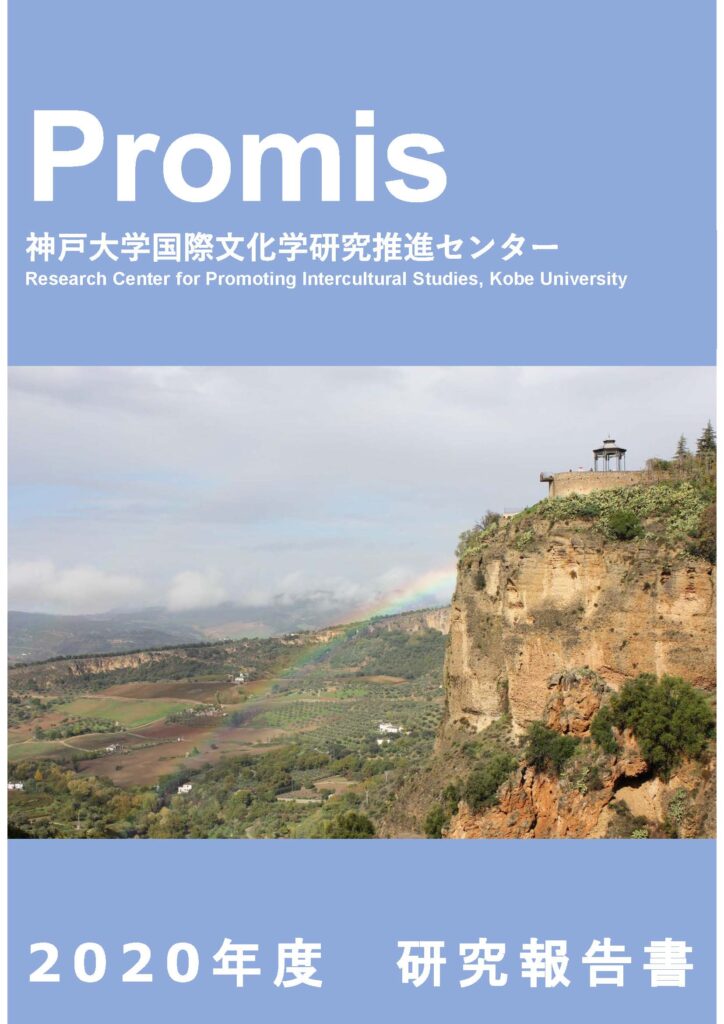
編集・制作/Editors:
HARADA Suguru, KOBATA Rika, KOBAYASHI Rune, SATO Ryosuke
発刊日/Date of Publication:
31 March 2021
発行者/Publisher:
Research Center for Promoting Intercultural Studies, Kobe University
2020 Annual Research Report: Contents 
| I.論文/Articles | |
| 【論文】 日中対訳小説における日本語と中国語の非情受身文の対応関係について 陳 婧璇(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 7-27 |
| 【論文】 Comparing Regional Integration Projects—Institutional arrangements for solving collective action problems in the EU and ASEAN— Suguru HARADA(Promis Research Fellow) | 28-43 |
| 【論文】 カール・ミュレンホッフの歴史叙述—神話学派の歴史認識の事例として— 馬場 綾香(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 44-60 |
| 【論文】 タイ人の面子概念に対する一考察—日本人と中国人との比較を基に— 林 萍萍(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 61-76 |
| II.著書紹介/Authors' Introduction of Book | |
| 『翻訳文学紀行Ⅱ』(「日本語(古文)文学」執筆担当) 南郷晃子(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 79 |
| 『数学史事典』(「ケンブリッジ・トライポス」「ミステリーの中の数学」「ルーカス教授職」執筆担当) 野村恒彦(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 80 |
| III.研究員による本の紹介/ Book Presentation | |
| 本紹介 野村恒彦(国際文化学研究推進センター 協力研究員) | 83 |
| IV.2020年度セミナー報告/ Semnar Reports in the year 2020 | |
| V.2020年度研究プロジェクト概要/ Research Projects in the year 2020 | |
| 「美しい」キリスト者の検証—「郷土」における宣教イメージの反転— | 111 |
| 共生とコンヴィヴィアリティ—グローバル・シティズンシップの可能性と限界— | 112 |
| 記憶のマテリアリズム—「モノ」、移動/移民、ナラティヴの領域横断的研究の総括と出版— | 113 |
| 2002年〜2018年のベトナムにおける日本の翻訳書に関する研究 | 114 |
| 移民社会におけるセミパブリック・スペースの重要性とその利用実態に関する研究 | 115 |